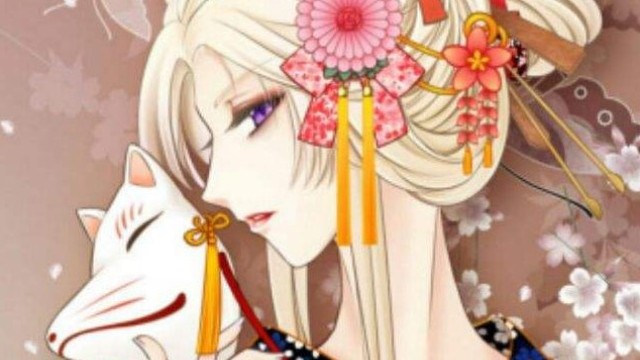日语论文范文:关于日语中食感相关的拟声拟态词的研究
2. 食感のオノマトペの分類
食感覚のオノマトペは感覚で捉えた食物の特徴を言語音で模倣したもので、食物の特質を強く反映している。日本語にはなぜ、食感覚のオノマトペが極めて多いかというと、その背景について、国立国語研究所の南不二男は、『食の文化フォーラム・食のことば』という本に、日本語には食物を形容する言葉の種類が少ないことを指摘し、それを補うため、比喩表現やオノマトペの存在を挙げている。
それで、早川文代をはじめ、調理科学分野の専門家たちが2003年に行った食感研究の専門家へのアンケートとインタビューによると、日本の食感覚のオノマトペは445語の用語から成るリストが得られた。一方、外国語の研究結果と比較すると、英語やドイツ語で約100語、フランス語227語、中国語144語と、日本語の数の多さが見られる。これらの研究は調査方法が異なるため、厳密には比較できないが、日本語の食感覚を表すオノマトペが極めて多彩であることは言えるであろう。
なお、これほど数の多いオノマトペは、どのようなときに使われるかに関しては、以下の例から見ればわかると思う。「ぴりっとしたキムチが美味しい」、「じゅうじゅうと音を立てている焼きたてのビーフステーキ」など、食感覚のオノマトペは食卓でコミュニケーションを円滑するのに欠かせない。それから、「このパンはもっちり仕上げました」や「さくさくのコロッケが揚げたてです」など、食物の作る側からの情報伝達にも決してなくてはならない存在であろう。または、食品研究や感覚研究の場においても、食感覚のオノマトペは重要な役割を果たしている。例えば、評価するとき、「ぱりぱり」「かりかり」「がりがり」のように、言葉を変えると、結果的には大きな違いが発生する。現代において、調理外部化、産業化が進むなか、「人々がそれをどう感じているか」を客観的に捉えるのがますます重要になり、社会的にもニーズが高まっている。
食感覚のオノマトペの数の多さ、社会的役割、日常生活に使用される頻繁さが大きな背景として、いかに正確に使い、受け入れるというのが差し迫っている。
2.1評価による分類
本章では、食感のオノマトペをまず評価により、分類していきたいと思う。人々がどのようにオノマトペを使い、食物への好き嫌いを表現するのか、食べていない人にどうすればその食物の食感を伝えるのかを実例を見ながら解明したいと思う。
評価で食感覚のオノマトペを分類すると、かなり個人的な好みで異なる場合もあるが、ここでは、この差を考慮せず、一般的に論じたいと思う。その食品に期待される属性があるか否かにより、プラスとマイナスで分けられる。すなわち、一つの言葉を用いて、「○○しておいしい」がプラスだとし、その反面、「○○してまずい」がマイナス評価だとするのである。「○○」の部分にオノマトペを入れて、受け入れられると、成立するということである。
2.1.1 プラス
この節では、プラス評価のオノマトペを検討しよう。以下の具体例を見てみよう。
(1)マスを酒と酢でしめて臭みを抜いた酢の物で、さっぱりしていてうまい。
「さっぱり」は味覚などが淡泊なさまを表す。私たちは、この酢の物に対して、味の淡泊さを期待する。この欲求が満たされるとおいしく感じ、満足する。
(2)アーモンドをシュガーコートし、かりっと香ばしくフライしました。
「かりっと」というのは、堅いものや乾いたものを噛み砕くときに出る音を表す語である。ここは、アーモンドに対する歯応えと歯切れ音を表すとともに、その歯ごたえと音を好ましいと思う気持ち、すなわちその食品に対するプラス評価も表す。
(3)この炊飯器だと、まきで炊いたようにご飯がふっくらと炊きあがる。
「ふっくら」はよく弾力に富み、いかにも柔らかい感じにふくらんでいるもののようすを表すときに使われている。ご飯に対しては、透明感のある純白色、ぷりぷりの歯応え、甘味のある食感が求められている。口に入れる前に、視覚で感じるもの、つまりご飯の形態への期待は一粒一粒が膨らむ状態である。「ふっくら」を通して、ご飯が思った通りにできあがた時の満足感を伝える。
(4)セロリは香りがあり、生のものはしゃきしゃきと歯ざわりがよいのでサラダに好適だ。
「しゃきしゃき」は歯切れよい音・感触を表す言葉である。新鮮なセロリは水分を含み、やや硬めの歯応えである。逆に賞味期限がすぎたものはぐにゃぐにゃで、柔らかくて変形しやすい。サラダに使うセロリであるため、一定的な新鮮度を求める。この条件が満たされたとたん、食べる側の期待に答えられ、プラス評価をつける。
以上の例は全て、オノマトペ自身が担うプラス評価の例である。マイナス評価については、次節で考察する。
2.1.2 マイナス
この節では、前節の続きとして、マイナス評価をつけるときに使うオノマトペの用例を見てみよう。
(5)ぼそぼそに乾いたパンを噛みながら山中をさまよった。
「ぼそぼそ」は食物の水分やうまみが少なく、まずくなった様子を表す。パンがよく発酵されたと、中に空気が入り、噛み心地がいい。この場合は、乾いたパンの喉に詰まっている様子を「ぼそぼそ」を使い、マイナス評価を表す食感覚のオノマトペになる。
(6)こんなかすかすの大根を売るなんてひどい店だ。
「かすかす」は食物の水気が乏しいさまを表す。ここでは単に乾燥感を表すだけでなく、食品に対するマイナス評価を含む。どの食品にも一定の水気が期待されているにもかかわらず、それが満たされないから、マイナス評価になる。
(7)こんな乾物が食べるか。かちかちして板のようだ。
「かちかち」というのは、非常に堅いもののようすを表す。乾物は水分が全くなくて、非常に乾いてるもの。例文を見ると、「板のよう」という、堅さが想像できる。こういうような食感の食物は、誰にでも好きにならないので、マイナス評価に属する。
マイナス評価に属するオノマトペは、53語の範囲内では数が少ないため、例は以上だけ出してみた。次節では、まとめとして、食感のオノマトペを評価により分類について説明したいと思う。
2.1.3まとめ
2.1.1に出てきた例文はどちらでも、食べる側が予想通りの味わいを持っている食物を食べられて、食品から満足感を得られた例である。だから美味しく感じられ、プラス評価を与える。その反面、4.2では、どちらでも本来あるべき味わい(例文の中では水気、あるいは柔らかさ)が欠けているので、美味しさが破壊され、まずくなって、マイナス評価をつける。
言葉は発展の流れとともに、使える場合が定着してきた。そのうち、言葉自身が使う場の言語的色彩のため、好き嫌いに分けられた。すなわち、プラス表現したいときは必ずこれらの言葉を使い、マイナス気分を表現したいとき、それらの言葉を使ったら不自然な文になる。
ここで、早川ほか(2000)井川(1991)森(1995)などを参考にして、53語の食関係のオノマトペを属性にもとづく評価分類は表1にしたものである(冒頭にや行、ら行、わ行に属する語が53語にないため、考慮しない)。
|
|
あ |
か |
さ |
た |
な |
は |
ま |
|
プラス(+) |
あっさり あつあつ |
からっ かりかり こってり こりこり |
さくさく さらさら さっぱり しこしこ しっとり しゃきしゃき しゃりしゃり しゅわしゅわ すーすー |
つるつる とろとろ |
|
ばりばり ぱりぱり ひんやり ふわふわ ふっくら ぷちぷち ぷりぷり ぷるぷる ほくほく ほっかほか ぽきぽき ぽりぽり
|
まったり むちむち |
|
マイナス(-) |
|
かすかす かちかち ぎとぎと |
ざらざら |
|
|
ぱさぱさ ぼそぼそ |
もそもそ |
|
どちらにも分類できない |
|
かっか がりがり きしきし ぐにゃぐにゃ |
ずるずる |
どろどろ |
にちゃにちゃ ぬるぬる ねっとり |
ぱらぱら ひりひり ふにゃふにゃ べたべた ぼりぼり ぽろぽろ |
|
表①(筆者による)
表①から見ると、53語のうち、プラス表現のオノマトペの数は圧倒的多いのであることが分かった。
さらに性質から53語を分類すると、以下のようなものがある。
まずはプラス評価に属するものをテクスチャー、濃淡、温冷、聴覚で分類すると、以下のように分類できる。
テクスチャー:からっ、かりかり、こりこり、さくさく、さらさら、しこしこ、しっとり、しゃきしゃき、しゃりしゃり、とろとろ、ばりばり、ぱりぱり、ふわふわ、ふっくら、ぷちぷち、ぷりぷり、ぷるぷる、ほくほく、ぽりぽり、ぽきぽき、むちむち
濃淡:あっさり、さっぱり、こってり、まったり
温冷:あつあつ、すーすー、ひんやり、ほっかほか
聴覚:つるつる、しゅわしゅわ
次にマイナス評価に属するものを乾湿、舌ざわり・口当たり、硬軟で分類すると、以下のように分類できる。
乾湿:かすかす、ぱさぱさ、ぼそぼそ、もそもそ
舌ざわり・口当たり:ぎとぎと、ざらざら
硬軟:かちかち
以上の分類を見ると、プラス評価の組では、テクスチャーを表すものが最も多い。次いで、濃淡を表すもの、温冷を表すもの、聴覚で感じたものが続く。これに対して、マイナス評価を表すものは、乾湿を表すものが最も多いが、舌ざわり、硬軟を表すものは少ない。数から見れば、日本では、テクスチャーのあるものが受け入れやすく、最も日本人の口に合うとことが分かった。なお、表1に出てきた結果から見ると、好きな食物へ対して人々は豊富に言葉を使い、そのおいしさを他人に伝える習慣がある。その反面、好きではない食物に対しては形容する興味が薄いということも本章では分かった。
2.2 感覚による分類
本章では、食感のオノマトペを感覚にもとより分類したいと思う。感覚をさらに触覚、聴覚、視覚及び複合感覚の四つに分けて具体的に実例を分析しながら分類していきたいと思う。
2.2.1 触覚
まず、触覚的経験を感じるときの感覚を見よう。触覚はさらに、1、温冷覚2、痛覚3、テクスチャーの三つに分けられる。
ア.温冷覚
最初は温冷覚に関わるものを見てみよう。まずは温かさ、熱さを連想させるものから見よう。
(1)道ばたで買ったほかほかのたい焼きを、かぷっと頬ばるときのうまさ。
ここでの「ほかほか」というオノマトペは熱気がこもっていて湯気が上がるほどの状態であるようすを表す。たい焼きを焼きたてたとき、高温で焼いた結果、表面がさくさくで少しだけ固めにしている、中を食べると、あんがあつあつで、とけるような旨みである。噛みきったときに、中からあんの湯気が上がってくるような画面は、普段の経験を回想すると、想像し難くないであろう。
(2)かりっと皮がくだけると、あつあつの具が口に広がる。
「あつあつ」というのは、非常に熱いこと。ここでの食物は、餃子類だとすると、皮を砕けて、舌が中の具に触ったときに、具の温度、つまりその熱さに感じられるであろう。
次は冷覚に関わるものを見てみよう。「ひんやり」「ひやっ」などがある。例でみると、
(3)ひんやり、つるっと喉ごしを楽しむ夏の麺。
「ひんやり」は冷たい感触・雰囲気であるさまを表す。後半の文のいうとおりに、喉から麺の冷覚が感じられる。真夏で涼麺を喉からすすり込んだときの爽やかさを表現できる。
(4)氷の上に盛られた鯉のあらい。一切れ口に入れるとひやっと舌に冷たい。
「ひやっと」も「ひんやり」と同じように、冷気を感ずるさまを表す。「ひんやり」よりさらに冷たい感じである。
イ.痛覚
次に痛覚に関しては、例は以下のように。
(5)タイ料理のエビのスープは、舌がひりひりするほど辛くて味がわからなくなる。
「ひりひり」は皮膚や粘膜が小刻みに刺されるような痛みや辛みを持続的に感ずるさまを表す。普通は唐辛子、キムチ、カレーのようなものを形容するときによく使う。
(6)ミントのガムを噛んだあとは、口の中が息をするたびにすーすーする。
「すーすー」というのは、空気が出入りするたびに冷たく感じるようす。使える範囲は相対的に狭いのである。おもに、ミント成分の含む飴やガムなどを食べるときに使う。
ウ.テクスチャー
テクスチャーに関するオノマトペの数は厖大であるが、ここでは便宜上、二つだけ見てみよう。
(7)この芋、いくら煮ってもがちがちで食えたもんじゃない。
「がちがち」というのは、異常に堅いさまを表す言葉である。芋というのは、もともと堅くても普通は時間をかけて煮ったら柔らかくなり、歯に切られる柔軟度になる。しかし、ここでは、特例として、芋の異常な堅さを表現する。
(8)納豆はねばねばした糸が味のきめてなんだ。
納豆の特質として、粘り気が強くて糸を引く。「ねばねば」は糸を引くような粘り気があるさま、またはそういうものを表す。だから、ここでは、口当たりがべたつく納豆には「ねばねば」という語が最も適切であり、実際にもよくペアとして出現する。
2.2.2 聴覚
ここでの聴覚とは、ものを食べるときの歯切れ音や咀嚼音、あるいは喉ごしのよい食物がすすり込むときの音などである。すなわち、聴覚を表す食のオノマトペはすべて擬音語であること。例を挙げると、以下のようなものがある。
(9)とりたての生牡蠣に、レモン汁をかけてつるつると食べるそのおいしさ。
生牡蠣の表面にレモン汁がかけてあるので、すべすべになるのである。だから、食べるときにも滑やかで、汁が舌と摩擦した音が必ず出る。その摩擦した音を言語音、つまりオノマトペで表すと、まさにこの「つるつる」である。
(10)さくさくとりんごをかじる。
新鮮なりんごを食べると、水分が多いうえ、もろくて歯応えがいい。このときが発した音は、歯切れ音のことである、誰にも経験があるのが、人がりんごなどを食べているときに、その歯切れ音だけ聞いても、食べたくなるような、りんご自身の新鮮感が伝えられるのであろう。
(11)せんべいをぱりっと噛む。
「ぱりっと」は硬くて薄いものを噛み砕くときの音を表す。せんべいはやや硬いので、噛むときに、音は必ずする。その音をまねしたものは、「ぱりっと」のような言葉である。
2.2.3 視覚
視覚で感じた食感覚のオノマトペは一番数少ないが、それはまだ食べていないうちに、目で見た食物の様子であるもの。すなわちその食物の形態である。字面通りに擬態語に入る。例を見ると
(12)ご飯を冷蔵庫に入れておいたらぽろぽろだ。
「ぽろぽろ」とは、軽いものが一つ一つ落ちるさま。または、ものの水分がなくなって小さな粒状にまとまっているさま。ご飯を炊きたていたときに、粘り気もあって、膨らんでいるようすに対して、冷えたご飯は、一粒一粒ばらばらで、粘り気が抜けたのである。ここでは接触を伴わずに完全に視覚の表現としてのオノマトペである。
2.2.4 複合感覚
1.3に述べたように、一つの語で、二つ以上の意味が含むというのが少なくない。ここでも、同じ語形で人間の複数の身体器官で感じたものを同時に表すことが可能である。以下の実例を見ながら詳しく分析する。
ア.「触覚―視覚」
(13)ぎっしりと詰まった新鮮でぷりぷりのカニ身。
ここの「ぷりぷり」は視覚的体験か触覚的体験か、どちらに限定するのは難しい。目で捉える視覚感受としても弾力のあるようすが見られる上、歯応えとしての体験も表すことができる。視覚と触覚の感覚が相互に関わりあっていると見るべきであろう。
さらに例を見ると、このようなものがある。
(14)ボールに室温にもどしたバターと砂糖半量を入れ、白っぽくふんわりするまで木ベラですり混ぜる。
ある種の形状を視覚で捉えている。あるいは、経験的に知っていることから、視覚表現が成り立つ。この場合は、また、木ベラによる間接的な接触が認められるので、触覚的経験が関わっているといえる。
イ.「触覚―視覚―聴覚」
(15)お茶漬けをさらさら食べる。
ここの「さらさら」は、音(聴覚)を表すのか、素早くかき込む様子(視覚)を表すのか、もしくは舌ざわりや喉ごし(触覚)を表すのか。それはどちらの一つだけに限定することはできない。むしろ、この三つの感覚の重ねだというほうが説得力があるであろう。
(16)たらこ・塩数の子・塩いくらをセットにしました。一粒一粒ほぐして塩漬けにしたぷちぷちのいくら、スケソウダラの成熟卵を生のまま塩漬けにしたさらのたらこ、ニシンの卵を塩漬けにしたコリコリの数の子。
ここの「ぷちぷち」は口の中の感覚のみならず、視覚的印象(粒状のものが細かくぎっしり詰まっている様子)及び聴覚的印象(噛みきったときの音)のすべてを表すと考えられる。
ウ.「触覚―聴覚」
(17)ちょっともそもそした表面で、さらに、中の生地もかさかさして、何か喉乾きそう。
「かさかさ」というのは、まず、触覚として水分の少なさ、つまり乾燥感、または乾燥であるため、噛むときの破砕音。「かさかさ」の特殊なところは、その音感自身に乾いた感じがあって、このような音を立てるようなものが、水気を失って乾いた状態のものであることが多いから、触覚的にも乾燥感の感じるものが多いというところである。
(18)歯がきしきしするほどタンニンが強いですが、厚みのある味わいなので、全然気にならずに美味しく飲めます。
「きしきし」は堅いものなどの小さくすれる音を表す。すれる音であるから、摩擦音としては聴覚の面でのオノマトペ。なお、もう一面は、摩擦するときの歯応えとして、触覚方面のオノマトペとして扱われる。
エ.「嗅覚―味覚」「味覚―触覚」
(19)からし明太子だと、辛味がつんとして、それはそれでおもしろい味だ。
「つんと」というのが、強烈な匂いや味を表す。口と鼻がつながっているため、口が刺激的な味を味わうとき、鼻もその感覚を受け入れ、影響されるということで、嗅覚と味覚の複合感覚を表現するオノマトペである。
(20)スパイスをきかせた料理にも、デビルということばがしばしば使われる。で、これが
べられないくらいにひりひりしているのかと思うとそれほどでもない。
ここの「ひりひり」は味覚と痛覚の二つの感覚経験を表すと考えられる。味覚的刺激・嗅覚的刺激・触覚的刺激の三つは、そもそも明確に分けられないのではないか、という疑問が生じる。が、ここでは便宜上、舌ならば味覚、鼻ならば嗅覚、それ以外の皮膚感覚ならば触覚というように、刺激を感知する器官によって感覚を区分し、それらの相互作用を検討した。
オ.「視覚―聴覚」
(21)皆が混じってカウンターに並び、ずるずるとラーメンを食べる。
麺類などを素早く啜りあげるさまを表すずるずるは、聴覚が顕著な場合と視覚が顕著な場合がある。しかし、どちらかに限って表現するのではなく、むしろ聴覚と視覚の両方を表すと考えられる。これは、素早く啜り上げるとき、「ずるずる」という啜り音が立つ。
カ.「視覚―味覚」
(22)お肉の脂がこってりした仔羊や牛肉。
「こってり」が見た目の濃厚さと味覚を表すとき、油分の多い濃厚な味を同時に表すことができる。この触覚と味覚、そして視覚の意味の間の関係も触覚的に「こってり」しているものが視覚的特徴を有することが多いという私たちの経験を踏まえている。
以上、食感覚のオノマトペを感覚により分類整理した。五感で感じたものを器官別に分類され、どちらかの器官で感じるものが一番顕著であるかによって、オノマトペを選択することができる。すなわち、食前に食物を形容したいときは、視覚上のオノマトペを選択し、匂いの強い食物の食感を他人に伝えたいときは嗅覚を前提とし言葉を選択するということである。